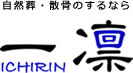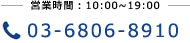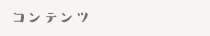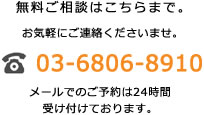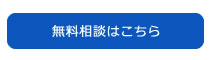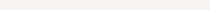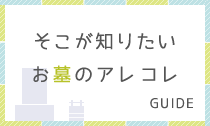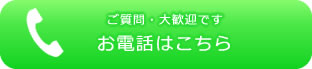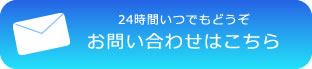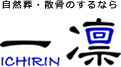【衝撃】墓じまいで土葬の古い骨が出てきたら?

再火葬と納骨の手順をわかりやすく解説
墓じまいの際に先祖の土葬の骨が出てきた場合、どう対応すればいいか迷う方は少なくありません。
この記事では、土葬の歴史や骨の状態、法律上のルール、具体的な改葬手順まで、詳しく解説します。再火葬や納骨・散骨のポイントも丁寧に紹介します。
- 土葬の可能性があるお墓の墓じまいを検討中の方
- 土葬骨の手続きや衛生的な対処法を知りたい方
- 再火葬後の納骨・散骨など新しい供養を検討中の方
1.【土葬の歴史】 地域差と残る骨の特徴

📌 土葬の文化と地域性の違い
土葬は明治時代まで日本全国で行われていた一般的な埋葬方法ですが、火葬の普及には地域差がありました。
火葬普及の遅れ : 東北や北海道などの寒冷地や、地方の農村部では、火葬場整備の遅れから比較的長く土葬が残りました。
火葬普及の速さ : 関東以西の都市部では、明治初期から衛生上の観点や土地不足から火葬が急速に普及しました。
お墓の形式も多様で、板棺、石囲い、藁棺などがあり、これらの違いが骨の残り方に影響します。
土葬の骨が出てきたということは、その地域が比較的古い歴史を持つか、火葬が遅くまで行われていなかった証拠と言えます。
📌 骨が残るか残らないかの分かれ道
骨が残っているかどうかは、主に土壌の性質に左右されます。
| 土壌の性質 | 乾燥した砂地 |
|---|---|
| 骨の状態 | 骨の形状が残っていることが多い |
| 特徴 | 100年以上前の骨でも発見されることがある |
| 土壌の性質 | 湿った粘土質・酸性土壌 |
|---|---|
| 骨の状態 | 粉状・ほとんど残らない |
| 特徴 | 数十年で骨の主成分が溶けて土に還る |
掘り出す前に土壌の性質からある程度骨の状態を予想しておくと、後の作業や再火葬の計画が立てやすくなります。
特に骨が原型をとどめていた場合、驚かれるかもしれませんが、適切に清めて(洗骨し)再火葬することで、現代の供養に繋げることが可能です。
2.【法律と手続き】 火葬・改葬のルール

📌 現代の法律が定める「埋葬」の原則
現行の日本の法律では、「墓地埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)」に基づき、遺体は火葬後に埋葬することが原則と定められています。
土葬の骨に関して、法律に明確な規定はありませんが、多くの施設では「火葬済み」であることを受け入れの前提としています。
このため、土葬の遺骨は事実上「火葬扱いではない」と解釈され、現代の納骨堂、永代供養墓、樹木葬などの新しい供養施設では、「火葬証明書」が求められることが一般的です。
📌 骨を移動させるための「改葬許可申請」
墓じまいの際に土葬の骨であれ火葬の骨であれ、お墓からお骨を取り出し、別の場所に移す行為はすべて「改葬(かいそう)」にあたり、行政手続きが必要です。
お骨が現在埋葬されている市町村の役場に対し、「改葬許可申請書」を提出し、「改葬許可証」の発行を受ける必要があります。
この許可証がないと、お骨の移動や新しい納骨先への納骨は法律違反となります。
3.【改葬の具体手順】 安全に進める流れ

墓じまいで土葬の骨が出た場合の、法的な手続きと現場での具体的な手順を順を追って解説します。
ステップ1:行政手続き(改葬許可証の取得)
土葬の骨を掘り出す前に、必ず市町村の役場で改葬許可申請を行います。
新しい納骨先の決定 : 再火葬後の納骨先(寺院、霊園、散骨業者など)を決め、「受入証明書」を発行してもらいます。
既存墓地の証明 : 現在の墓地の管理者に、お骨が埋まっていることを証明する「埋蔵証明書」を発行してもらいます。
申請と許可 : 上記の証明書を添え、役場に「改葬許可申請書」を提出し、「改葬許可証」を取得します。
この手続きはご自身で行えますが、行政書士に代行を依頼することも可能です。
ステップ2:現場作業(掘り出しと洗骨・再火葬)
改葬許可証を取得した後、いよいよ現場での作業に移ります。
土葬の骨の慎重な掘り出し : 現場の石材店が立ち会い、細心の注意を払って掘り出し作業を行います。骨が粉状になっている場合でも、土ごと丁寧に集めます。
洗骨(せんこつ)の実施 : 土や泥が付着した土葬の骨を洗浄・消毒・乾燥させる「洗骨」は、次の供養に進むために推奨される工程です。洗骨を求める火葬場が多いですが、地域や火葬場によっては洗骨せずそのまま再火葬を受け入れる場合もあるため、事前に確認が必要です。
再火葬 : 洗骨・乾燥を終えたお骨、または火葬場が認めた状態で火葬場へ運び、再火葬を行います。ここで火葬証明書が発行され、現代の納骨施設に受け入れられる状態になります。
4.【再火葬の必要性】 納骨や散骨に向けた準備

再火葬は、法律上の要件を満たすだけでなく、新しい供養を行う上での衛生的な準備としても非常に重要です。
📌 再火葬が求められる主な理由
| 理由 | 法律・施設ルール |
|---|---|
| 詳細 | 多くの納骨堂・樹木葬が「火葬証明書」を前提としており、再火葬が必要になる場合が多い。 |
| 理由 | 衛生面・心理面 |
|---|---|
| 詳細 | 長年の土や泥が付着しているため、洗浄・消毒・火葬で清潔な状態に整える必要がある。 |
| 理由 | 散骨の準備 |
|---|---|
| 詳細 | 散骨には粉骨が必要。洗骨と再火葬を経ることで、安全に粉骨加工ができる。 |
再火葬は、ほとんどの納骨施設で必要とされますが、一部の寺院や地域によっては、洗骨のみで土葬の骨の受け入れを認めるケースも存在します。
必ず事前に納骨先のルールを確認しましょう。
📌 再火葬後の新しい供養の選択肢
再火葬を終えたお骨は、現代の様々な供養方法を選べるようになります。
永代供養・納骨堂 : 継承の不安がない、都市部での供養
樹木葬 : 自然の中で眠りたいという願いを叶える供養
海洋散骨 : 海に還す自然葬。特に土葬で土に還ることを選ばれたご先祖様にとって、広い海へ還るという選択は、思想的に親和性が高いと感じる方も多いです。
5.【注意点とまとめ】 宗教・文化・衛生の配慮

📌 作業時の配慮と注意点
土葬の骨を掘り出す作業は、心理的な側面と衛生的な側面に最大限の配慮が必要です。
家族・宗教的な慣習の尊重 : 掘り出しや再火葬を進める前に、ご家族や菩提寺と十分に相談し、宗教的な慣習や故人の文化的な背景を尊重することが大切です。
文化財の可能性 : 万が一、歴史的・文化的な価値があるお骨や副葬品を発見した可能性がある場合は、自治体の文化財課や専門家に相談しましょう。
衛生管理の徹底(PPE) : 掘り出し作業に立ち会う際は、マスク、手袋、消毒液などを徹底的に使用し、衛生面に十分配慮しましょう。
📌 土葬の骨が出ても焦らず手順を守る
墓じまいで土葬の骨が出ても、決して焦る必要はありません。
大切なのは、「改葬許可証」の取得、そして「洗骨」と「再火葬」という現代の供養に繋ぐための手順を守ることです。
石材店、行政書士、再火葬や納骨の専門家と連携しながら進めることで、ご先祖様を敬い、安全に新しい供養の形へ繋げることが出来るでしょう。
東京や関東近県で海洋散骨をご検討でしたら、ぜひ海洋散骨オフィス一凛にご相談ください。
より多くのお客様の声はこちらからご覧いただけます! → 海洋散骨オフィス一凛のGoogle口コミはこちら
散骨でお困り、お悩みがありましたら、いますぐ下記までご相談くださいませ。
旦那のお墓は・・・女性のお墓に対する考え
今までの檀家制度は先祖のお墓に入る・・・これが当たり前でした。結婚した女性は、夫側のお墓に入る。 今まで当たり前だった、そんなお墓の習慣を疑問に思う女性が増えている事をご存知ですか?

思い出の場所で静かに送ってもいいのか。
船を使わない散骨に迷う気持ちは自然です。
後悔しないための配慮と判断軸を整理します。

知らなきゃ損!葬儀費用の一部が戻る給付金制度
それが葬祭費給付金制度で最大7万円の支給も
申請しないと一円も戻ってこないので要チェック

死亡後に届く請求書、払うべきか迷っていませんか。
その支払いが、相続放棄を不可能にする場合があります。
損をしない判断基準を、この記事で整理します。

供養方法の一般的なお墓 vs 樹木葬 と 海洋散骨
どの供養方法が良いのか悩んでいませんか?
最新データの数字を基に選び方を解説します。

宗教に縛られない供養は失礼なのか。
そう感じる人が今、増えています。
選ばれる理由には社会の変化があります。

散骨は法律や条例違反ではありません。
ただし手順やルールを間違えると違法も。
わかりにくい注意点や実例を詳しく解説。

お墓を開けて骨壺に水が溜まっていた。
それは珍しいことではありません。
原因と対策を現場目線で解説します。

葬儀の広告料金は、本当に信用できるのでしょうか。
見積もりが倍以上に膨らむ背景には、明確な理由があります。
後悔しないために、費用のカラクリと対策を整理します。

公正証書遺言がオンライン対応になりました。
公証役場へ行かず自宅から作成できます。
条件と注意点を専門視点で解説します。

海洋散骨を選ぶ理由は一つではありません。
故人の願いを叶える供養としての選択。
そして遺骨の行方に向き合う現実的な選択。
散骨でお困り、お悩みがありましたら、いますぐ下記までご相談くださいませ。
散骨の一凛では遺骨の激安・格安の処分、他社よりも、どこよりも安い遺骨処分、海洋散骨をしております。