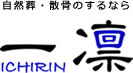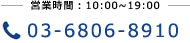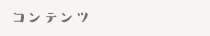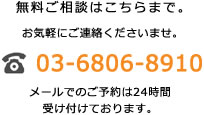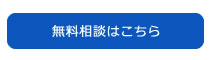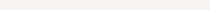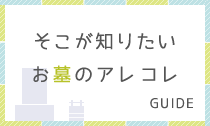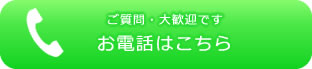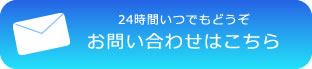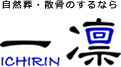日本で土葬はできる?法律と現実の壁を解説

火葬99.97%の国で土葬が難しい理由
火葬率99.97%の日本で土葬は法律上できるのか?
墓地埋葬法の仕組み、自治体条例、衛生問題、エンバーミングとの関係までを整理し、土葬が「事実上困難」とされる理由をわかりやすく解説します。
- 日本で土葬が可能か正確に知りたい方
- 宗教・文化上の理由で火葬以外を検討している方
- 火葬が当たり前な理由を客観的に理解したい方
1.【土葬の基本】土葬とはどんな埋葬か

土葬とは、ご遺体をお棺に入れ、土の中に直接埋める埋葬方法の一つです。
縄文時代から日本でも行われてきた歴史ある方法で、ご遺体をそのまま埋める方法のほか、甕(かめ)や桶に手足を折り曲げて埋葬する「屈葬」なども見られました。
土葬を行うには、棺桶を収めるための広い土地が必要となり、周囲の衛生に影響を与えないよう、2メートル以上穴を掘って埋葬する配慮が求められます。
世界的に見ると、キリスト教圏やイスラム教圏など、土葬を伝統的な埋葬方法とする国も数多く存在します。
2.【法律と制度】日本で土葬は許可されている?

現在の日本では、土葬が法律で明確に禁止されているわけではありません。
実際、「墓地、埋葬等に関する法律」では、「埋葬(ご遺体を土の中に葬ること)」と「火葬」の両方が認められています。
| 埋葬方法 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 火葬 | 約1,561,000件 | 約99.97% |
| 土葬 | 462件(うち成人88件) | 約0.03% |
出典:厚生労働省「衛生行政報告例 令和3年度」
しかし、このグラフが示すように、現実的には土葬の実施は極めて困難です。
その主な理由は以下の通りです。
✔ 土地の確保の難しさ
土葬には広い土地が必要ですが、特に都市部では土葬を許可する霊園や墓地がほとんどありません。
✔ 自治体による条例
「墓地、埋葬等に関する法律」の下、各自治体が独自の条例を定めており、多くの地域で土葬自体を禁止、または極めて厳しい条件を設けています。そのため、土葬ができる場所を探すのは非常に困難です。
✔ 具体的な事例
たとえば長野県の一部地域や沖縄県では、条例で土葬が完全に禁止されていない場所も存在します。また、特定の宗教法人系の霊園(例:イスラム教徒のための墓地など)では、限られた区画で土葬を受け入れているケースもありますが、一般の人が自由に利用できる機会は極めて稀ですし、費用も高額になりがちです。
✔ 衛生面への配慮
後述しますが、ご遺体の腐敗による地下水汚染や感染症のリスクが懸念され、住民の理解を得にくいという問題があります。
Q. 日本では火葬が義務付けられているの?
A. 義務ではありません。ただし、現実的に火葬以外は難しいのが現状です。
「墓地、埋葬等に関する法律」では「埋葬または火葬」が認められており、法律上は土葬も可能です。
しかし、多くの自治体が条例で土葬を禁止・制限しており、土葬を受け入れる墓地もほとんどないため、事実上は火葬が主流となっています。
3.【衛生問題】土葬が敬遠される理由

埋葬されたご遺体はいずれ土に還りますが、その過程での腐敗による衛生上の問題が、土葬の大きなデメリットとされています。
主な懸念点は以下の通りです。
✔ 地下水汚染のリスク
ご遺体の腐敗が進むと、バクテリアや分解生成物が土壌に浸透し、地下水を汚染する可能性があります。これにより、生活用水や農業用水が汚染され、感染症(例:過去にコレラなどのリスクが指摘された事例)を引き起こすリスクが指摘されてきました。
✔ 感染症の懸念
実際に、土中に埋められたご遺体が原因で、感染症が引き起こされた事例も報告されています。
✔ 風評被害
実際に、土葬墓地の建設計画が地元住民の強い反対により頓挫した事例も存在します。これは、生活用水の汚染や農業への風評被害を懸念する声が大きかったためです。
こうした衛生上の懸念が、土葬が広く受け入れられない理由の一つとなっています。
4.【防腐処理】エンバーミングとの関係

エンバーミングとは、「遺体衛生保全」とも訳され、ご遺体に殺菌消毒、防腐、修復、化粧などを施し、故人を生前の姿に近づける処置のことです。
これにより、腐敗や感染症を防ぎ、ご遺体を衛生的に長期間保存する技術です。
主に土葬を行う国々では、ご遺体からの感染症を防ぐために、このエンバーミングが広く行われています。
土葬をする際は、日本であってもエンバーミングは非常に重要とされています。
日本では、故人の死後、比較的迅速に火葬が行われるため、エンバーミングがおこなわれるケースは比較的少ないです。
しかし、土葬を検討する際には、衛生管理の観点からエンバーミングが不可欠となります。
補足:海外への“逆搬送”という選択肢
土葬が宗教上や文化的に不可欠な場合、ご遺体を海外の故郷へ送る「逆搬送(国際搬送)」という選択肢も存在します。
しかし、これは非常に複雑で、専門の国際搬送業者への依頼が必要になります。
主なプロセスと費用目安
✔ 防腐処理(エンバーミング): 衛生管理のため必須。
✔ 書類手続き : 出入国に必要な各種証明書や許可証。
✔ 航空貨物手配 : ご遺体専用の輸送手配。
✔ 現地の受け入れ手配 : 故郷での埋葬許可など。
これらのプロセスを含めると、費用は数十万円から100万円を超えるケースも珍しくなく、時間的、精神的な負担も大きいのが現状です。
5.【比較視点】土葬のメリットとデメリット

土葬には、他の埋葬方法にはない特徴があります。
ここでは、そのメリットとデメリットをまとめてご紹介します。
□ 土葬のメリットとは?
✔ 「土(自然)に還る」という思想 : ご遺体を火葬せずに土に埋葬するという方法は、古くから人々の間に根付く自然回帰の思想に基づいています。
✔ 環境負荷の低さ : 火葬とは異なり燃料を必要としないため、火葬時に排出されるCO2などを考慮すると、環境への負荷が低い埋葬方法とも言われています。
□ 土葬のデメリットとは?
✔ 多くの土地が必要 : 土葬を行うには、2メートル以上の深さや広い土地が必要となります。特に都市部では墓地などの土地が不足しており、新たな土葬墓地を確保することは極めて困難ですし、費用も高額になりがちです。
✔ 衛生面の問題 : 火葬と違い、土葬されたご遺体が腐敗すると、その影響が地下水に及ぶ可能性があり、感染症のリスクが懸念されます。
✔ 法的な制約と地域差 : 法律で禁止されていなくても、多くの自治体の条例で土葬が制限されているため、土葬を行える場所が非常に限られています。
6.【文化背景】日本人が感じる違和感

日本では法律上、土葬も認められています。
しかし実際には、火葬が圧倒的に主流であり、多くの日本人にとって土葬は「見たことがない」「なんとなく怖い」「異文化的なもの」と感じられているのが現実です。
「かつては土葬だったが、時代とともに減っていった」というより、現代の日本人の多くは、そもそも土葬の記憶も実感も持っていません。
火葬は戦後以降、制度面・衛生面・文化的背景から急速に普及し、いまや「火葬が当たり前」という常識が根付いています。
ここでは、「なぜ日本人が土葬を選ばなくなったのか」という感覚的な背景と、それに代わる現代的な埋葬スタイルを紹介します。
| 埋葬方法 | 埋葬スタイル | 費用相場(火葬含む) | 環境負荷 | 維持管理 | 実現性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般墓 | 火葬+墓地埋葬 | 約80〜150万円 | 低 | 必要 | ◎(主流) |
| 樹木葬 | 火葬+自然埋葬(樹木の下など) | 約30〜80万円 | 低〜中 | ※必要な場合あり | ◎ |
| 海洋散骨 | 火葬+海へ散骨 | 約10〜30万円 | 低 | 不要 | ◎ |
| 納骨堂 | 火葬+屋内に安置 | 約10〜150万円 | 低 | ※契約内容による | ◎ |
| 土葬 | 火葬なしの直接埋葬 | 約50〜100万円以上 | 中〜大 | 必要 | ×(極めて困難) |
※「維持管理」は霊園の規定や契約内容により異なります。
今後は、「供養のあり方」そのものを柔軟に考える人が増えることで、選択肢がさらに広がる可能性もあります。
従来の形式にとらわれず、自分たちらしい形を模索する時代に入っているのかもしれません。
7.【結論整理】土葬が現実的でない理由

日本では法律上土葬が完全に禁止されているわけではありません。
しかし、広大な土地の確保が難しく、自治体の条例による厳しい制限、さらには衛生面への懸念も伴います。
こうした制度的なハードルに加え、多くの日本人にとって「火葬」は当然の文化であり、「土葬」には不衛生、非近代的、怖いといった強い拒否感や嫌悪感があるのが現実です。
これは、長年にわたって築かれてきた死生観と衛生観念による「感情の壁」と言えるでしょう。
たとえ法的に整備されたとしても、日本社会において土葬が一般的な選択肢となる日は、まず訪れないはずです。
現代日本では、土葬は制度の問題ではなく、文化と感情によってほぼ不可能になっている埋葬方法だと言っても過言ではありません。
東京や関東近県で海洋散骨をご検討でしたら、ぜひ海洋散骨オフィス一凛にご相談ください。
より多くのお客様の声はこちらからご覧いただけます! → 海洋散骨オフィス一凛のGoogle口コミはこちら
散骨でお困り、お悩みがありましたら、いますぐ下記までご相談くださいませ。
旦那のお墓は・・・女性のお墓に対する考え
今までの檀家制度は先祖のお墓に入る・・・これが当たり前でした。結婚した女性は、夫側のお墓に入る。 今まで当たり前だった、そんなお墓の習慣を疑問に思う女性が増えている事をご存知ですか?

思い出の場所で静かに送ってもいいのか。
船を使わない散骨に迷う気持ちは自然です。
後悔しないための配慮と判断軸を整理します。

知らなきゃ損!葬儀費用の一部が戻る給付金制度
それが葬祭費給付金制度で最大7万円の支給も
申請しないと一円も戻ってこないので要チェック

死亡後に届く請求書、払うべきか迷っていませんか。
その支払いが、相続放棄を不可能にする場合があります。
損をしない判断基準を、この記事で整理します。

供養方法の一般的なお墓 vs 樹木葬 と 海洋散骨
どの供養方法が良いのか悩んでいませんか?
最新データの数字を基に選び方を解説します。

宗教に縛られない供養は失礼なのか。
そう感じる人が今、増えています。
選ばれる理由には社会の変化があります。

散骨は法律や条例違反ではありません。
ただし手順やルールを間違えると違法も。
わかりにくい注意点や実例を詳しく解説。

お墓を開けて骨壺に水が溜まっていた。
それは珍しいことではありません。
原因と対策を現場目線で解説します。

葬儀の広告料金は、本当に信用できるのでしょうか。
見積もりが倍以上に膨らむ背景には、明確な理由があります。
後悔しないために、費用のカラクリと対策を整理します。

公正証書遺言がオンライン対応になりました。
公証役場へ行かず自宅から作成できます。
条件と注意点を専門視点で解説します。

海洋散骨を選ぶ理由は一つではありません。
故人の願いを叶える供養としての選択。
そして遺骨の行方に向き合う現実的な選択。
散骨でお困り、お悩みがありましたら、いますぐ下記までご相談くださいませ。
散骨の一凛では遺骨の激安・格安の処分、他社よりも、どこよりも安い遺骨処分、海洋散骨をしております。