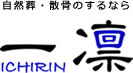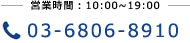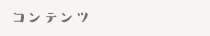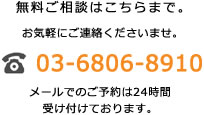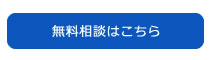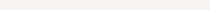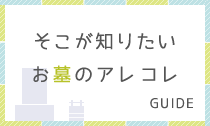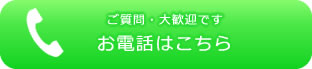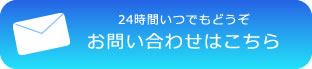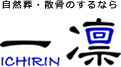散骨の歴史1200年:天皇と万葉集が語る供養

歴史で解明──日本人が選んだ自然に還る文化
お墓を持たない生き方は、決して現代のルーツではありません。
昔の人々は、風や山や海に故人を還してきました。
それは自然とともに生きる、日本人らしい供養の歴史なのです…
「お墓や遺骨は残すべきか、自然に還るべきか」──近年、供養のあり方が問い直されています。
「お墓を継ぐ人がいない」「子孫に負担をかけたくない」「自然に還りたい」という想いから、散骨が注目を集めています。
実はこの散骨、日本では決して新しい考え方ではありません。
この記事では、日本の知られざる散骨文化の歴史を、天皇の散骨記録や万葉集の和歌を交えながらわかりやすくご紹介します。
- 散骨の歴史やルーツを知りたい方
- 自然に還る供養を考えている方
- 伝統や文化としての散骨に興味がある方
1.【起源】散骨のルーツ:天皇が選んだ供養の歴史

✅ お墓の「当たり前」は近年のルーツ:昭和30年代以降の普及
現代人が抱える「お墓、どうしよう?」という悩みは、もはや他人事ではありません。
「お墓を継ぐ人がいない」「子孫に負担をかけたくない」といった声が増える中で、私たちはつい「日本は昔からお墓文化だ」と考えがちです。
しかし、庶民の間に広くお墓が普及したのは、実は戦後の昭和30年代の高度経済成長期以降といわれています。
それ以前、私たちの祖先はご遺体を土に埋める「埋葬」はしていましたが、現在の墓石のようなものは一般的ではありませんでした。
✅ 日本初の散骨ではない?淳和天皇が遺言で選んだ供養
散骨のルーツは飛鳥時代にさかのぼり、平安時代には火葬と並存していました。
特に注目すべきは、840年に崩御した淳和天皇です。
歴史書『続日本後紀 巻第九』には、天皇が自らの遺骨を京都の西山山頂で散骨するよう命じたと記録されています。
これは日本初の散骨ではありませんが、側近が「帝王が墓を持たないのは前代未聞」と反対した記述も残されています。
それでも淳和天皇は「自然に還りたい」という意思を貫きました。約1200年前から、権力者でさえ自然に還ることを願っていたのです。
✅ 平安時代は火葬と散骨が並存していた
古墳時代に権力者の象徴として巨大な古墳が築かれましたが、平安時代になると貴族の間で火葬が始まりました。
そしてこの時期、散骨もまた、火葬と並ぶ葬送方法の一つとして行われていた記録が残っています。
自然に還る「自然葬」とは、日本人にとっては根源的な供養の概念なのです。
2.【思想】万葉集が詠む「自然に還る」日本人の想い

✅ 玉梓の歌に込められた「愛と自然との融合」
日本最古の歌集『万葉集』にも、散骨された際の心情を詠んだ和歌が残されています。
「玉梓能 妹は玉かもあしひきの清き山辺に撒けば散りぬる」 「玉梓之 妹は花かもあしひきのこの山蔭に撒けば失せぬる」
この歌は、「愛しい妻は今、宝石になったのか、それとも美しい花となったのか…清らかな山のふもとにその骨を撒いたとき、彼女は静かに、自然と一つになっていった。」といった、作者の深い愛と、自然に還っていくことへの感慨が美しく表現されています。
この和歌は、日本最古の散骨の情景を描いた例としてしばしば引用されるものです。
✅ 日本人の根底にある「自然に寄り添う」死生観
大切な妻のご遺骨を山に散骨するという作者の心情は、散骨が当時、人々に身近な葬送方法であったことを強く示唆しています。
散骨とは、単に遺骨を処分することではなく、故人の魂を大地や海に託し、自然と溶け合っていく姿に「祈りのかたち」を見出す、日本人ならではの死生観と深く結びついた供養方法だったのです。
3.【変遷】散骨はなぜ消えた?檀家制度と墓埋法

✅ 檀家制度が散骨を減らした理由とは?
では、なぜ日本の散骨に対する意識が一時的に低くなったのでしょうか?
それは、主に江戸幕府の「宗教統制政策」として行われた檀家制度による影響が大きいと考えられています。
檀家制度によって、葬祭供養の全ては、それぞれが属する寺院が行うものと定められました。
これにより、納骨はお寺が管理する石造りのお墓へ行うという方式が徐々に浸透し、当たり前になっていったのです。
✅ 墓埋法制定時の盲点:法律と散骨の関係
さらに、現代では刑法の死体遺棄罪や墓地埋葬等に関する法律(墓埋法)によって、ご遺骨はお墓に納骨するのが常識だという考えを後押しした側面もあります。
しかし、これらの法律が定められた明治〜昭和にかけては、散骨という供養方法は一般的ではなく、法律制定時に散骨が想定されていなかったのです。
(補足:法務省は、墓埋法には散骨に関する直接的な規定はないとし、「節度をもって行われる限り違法ではない」との見解を示しています。)
4.【現代】石原裕次郎から広がる!散骨が選ばれる理由

✅ 石原裕次郎の散骨が社会に与えた影響
散骨が世間に広く知られるきっかけとなったのは、1987年、俳優・石原裕次郎さんが亡くなった際、ご遺骨が海に散骨されたことが報道されたことでした。
この報道が火付け役となり、「海洋散骨」という供養方法が改めて広く認知されるようになりました。
✅ 現代に蘇る3つの理由
現代に散骨が再び選ばれている背景には、大きく分けて3つの理由があります。
📌 承継問題 : 少子高齢化、核家族化により、お墓を継ぐ人がいない
📌 経済的負担 : お墓の建立費用や管理費用を子孫に残したくない
📌 自然への回帰 :「自然に還りたい」という本人の強い希望
時代とともに死生観や供養への考え方も変化し、お墓のあり方に疑問を持つ人が増えています。
✅ 自治体の理解も拡大中!広がる散骨の選択肢
かつては散骨が理由で改葬(お墓の引っ越し)の許可が下りないケースもありました。
しかし、現在では「散骨に対する世間的な理解の広がりから否定は困難」として、自治体が許可を出す事例も増えています。
このように、散骨は現代社会で確実に、そして急速に広まっている供養の選択肢なのです。
5.【総括】日本人が選び続けた自然に還る供養

散骨は、決して現代になって生まれた供養ではありません。
そのルーツは古代にあり、天皇の遺言として記録され、万葉集の和歌に描かれ、日本人の死生観とともに生きてきました。
そして、檀家制度や法律の整備によって一時的に姿を潜めながらも、自然へ還るという想いだけは途切れることなく受け継がれてきました。
現代に散骨が再び注目されているのは合理性だけでなく、私たちの心の奥にある 「自然と共に生き、自然へ還る」という古い感覚が呼び戻されているから なのかもしれません。
「1200年前に天皇が選んだ供養」「愛する人を自然へ託した詠み人の想い」それらは今、静かに私たちの選択肢として戻ってきています。
散骨とは、過去から現在へ受け継がれてきた、日本人らしい祈りのかたち──その歴史を知るだけで、供養の姿が少し豊かに見えてくるのではないでしょうか。
【参考文献】
東京や関東近県で海洋散骨をご検討でしたら、ぜひ海洋散骨オフィス一凛にご相談ください。
より多くのお客様の声はこちらからご覧いただけます! → 海洋散骨オフィス一凛のGoogle口コミはこちら
散骨でお困り、お悩みがありましたら、いますぐ下記までご相談くださいませ。
旦那のお墓は・・・女性のお墓に対する考え
今までの檀家制度は先祖のお墓に入る・・・これが当たり前でした。結婚した女性は、夫側のお墓に入る。 今まで当たり前だった、そんなお墓の習慣を疑問に思う女性が増えている事をご存知ですか?

墓を残すことは、親孝行なのか。
善意が、子どもの負担になることもある。
静かに増える「親不孝」の形を整理します。

散骨に対する考え方は、男女で大きく異なるのか?
男性はどこか理想を語り、女性は地に足がついている?
その違いや理由を実例とともに読み解きます。

散骨は供養をやめる行為なのか。
何もしない選択は冷たい判断なのか。
その違いを静かに整理します。

映画『水平線』が、私たちにある難題を投げかけました。
重大な罪を犯した人の散骨を頼まれたら!
散骨業者としての覚悟と、その先にある答えをお伝えします。

海洋散骨は、違法ではありません。
それでも行政は、評価も指針も示しません。
その沈黙には、明確な理由があります。

お墓は絶対?歴史から真実を探る。
今の常識は、わずか60年前の形。
心から納得できる供養を考えよう。

遺骨を家で守る時代は静かに変わり始めています。
無縁遺骨や墓じまいが増える背景があります。
遺骨を持たない家の未来を整理します。

近年、都市部に増えているビル型納骨堂
駅近で人気の裏にある注意点を探る
破産のリスクやメリットデメリットを解説

遺骨ダイヤと髪の毛ダイヤの違いとは?
生前に作れる選択が注目されています。
家族に迷いを残さない考え方を整理します。

厳粛なセレモニーだけが、お別れじゃない。
パーティーのように笑顔で見送る人も増加中
オーダーメイド海洋散骨、その魅力とは?
散骨でお困り、お悩みがありましたら、いますぐ下記までご相談くださいませ。
散骨の一凛では遺骨の激安・格安の処分、他社よりも、どこよりも安い遺骨処分、海洋散骨をしております。