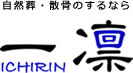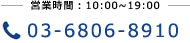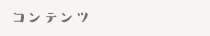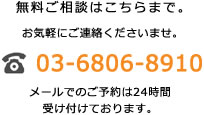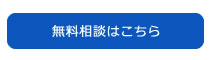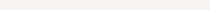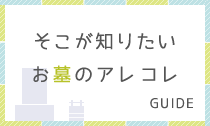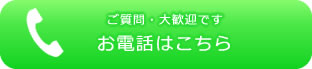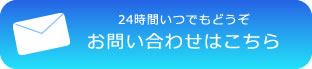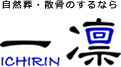墓じまいと供養の新しい形|お墓は本当に負の遺産なのか?

お墓は本当に必要なのか?常識が揺らぐ現代の供養事情
「お墓は長男や家族が代々守っていくもの」――そう考えるのが当たり前だと思っていませんか?
しかし、その常識は今、大きく変わりつつあります。
核家族化や経済的な理由、生活環境の変化によって、お墓を手放す「墓じまい」を選ぶご家庭が全国的に増えているのです。
特に、都市部に住む方が増え、遠方にあるお墓が大きな負担になっているケースは少なくありません。
年に数回しか行けないお墓は、本当に必要なのでしょうか?
もし、あなたが代々受け継いだお墓を「負担だ」と感じているなら、それはもしかすると「負の遺産」になりつつあるのかもしれません。
この記事では、現代のお墓事情と、負の遺産を残さないための散骨などの新しい供養の選択肢について、詳しく解説していきます。
- 墓じまいが増える社会背景と、その基本知識
- 新しい供養方法の比較と選択肢
- お墓に対する考え方と具体的なヒント
1.【墓じまいとは?】今あるお墓をどうする?基本を解説

墓じまいとは、今あるお墓を撤去し、墓地を更地の状態に戻すことです。
そして、お墓から取り出したご遺骨を別の方法で供養し直すことを指します。
もっと簡単に言えば、今あるお墓を「閉じる」ということです。
墓じまい後の永代供養や散骨といった供養方法は、多岐にわたります。
最近では、「新しくお墓を購入する」「お墓を建てる」という方は減少したと言われています。
こうした新しい供養方法を選ぶ方が、年々増えているのです。
特に、「夫の実家にあるお墓には入りたくない...」と考える女性も少なくありません。
海洋散骨のご依頼者様からも、「お墓の管理が大変だから」というお声を多くいただきます。
都心部で働き、地元のお墓に頻繁に行けないことも、墓じまいを選ぶ大きな理由の一つと考えられています。
墓じまいは「改葬(かいそう)」とも呼ばれます。
改葬には、役所から「改葬許可証」を取得するなどの手続きが必要です。
また、地域によっては散骨のような自然葬は「遺骨の引っ越し」に当たらないと判断され、改葬許可が認められないケースもあります。
手続き前に、自治体への確認をおすすめします。
【新しい供養方法の比較表】
| 供養方法 | 特徴 | 費用感 | 管理負担 |
|---|---|---|---|
| 合祀墓 | 他の方と一緒に納骨 | 比較的安い | 低い |
| 永代供養墓 | 寺院・霊園が管理 | 中程度 | ほぼ不要 |
| 樹木葬 | 自然の中で供養 | 中〜高 | 低い |
| 散骨 | 海・山などに撒く | 安い | なし |
| 自宅供養 | 自宅で保管 | 低い | 自己管理 |
2.【墓じまいの現状】全国で年間10万件以上!改葬数のリアル

墓じまいは、都心部だけでなく地方でも驚くべき速さで増えていることをご存知でしょうか?
地方で育った若者が都市部の大学に進学し、そのまま都会で就職することは今や当たり前です。
その結果、実家に残されたお墓が「遠い」「管理が大変」といった理由で、大きな負担になっているのです。
現在、全国で年間100,000件以上の「改葬」(墓じまい)が行われています。
これは単純計算すると、各都道府県のどこかで毎日約274件もの墓じまいが行われているということです。
この数字をどう感じるかは人それぞれでしょうが、決して少ない数ではないことは明らかです。
少子高齢化や核家族化が進む現代において、この墓じまいの増加傾向は今後も続くと予測されています。
3.【多死社会と供養】これからのお墓のあり方、どう考える?

少子高齢化とともに、「お墓を持たない選択」が現実味を増しています。
ここではその背景を見ていきましょう。
今の日本は、未婚率の上昇や出生率の低下が続き、人口減少を止めることができない状況にあります。
当然、お墓を代々受け継ぐ「承継者」の数も不足していくことは明確です。
2010年以降、日本の人口は一貫して減少していますが、一方で改葬数(墓じまい件数)は増加傾向にあります。
これは、少子化が進み「多死社会」と呼ばれる現代において、「お墓を継続して管理することが難しい」と感じる方が増えている何よりの証拠と言えるでしょう。
4.【先祖への思い】「お墓をなくす」ことへの抵抗感と向き合う

墓じまいを考える際、多くの方が「ご先祖様に申し訳ない…」「自分の代でお墓をなくしてしまうなんて…」と葛藤を感じる方も少なくありません。
この抵抗感は、先祖を敬う気持ちから来るものであり、決して間違った感情ではありません。
しかし、ここで一度立ち止まって考えてみませんか?
もし、お墓の管理が子孫にとって大きな負担になっているとしたら、ご先祖様は本当にそのことを望むでしょうか?
「子孫に負担を押し付けてまで、お墓を守ってほしい」と考える先祖は、おそらくいないでしょう。
あなたがもし、未来の先祖になったとしたら、子孫にどのような供養を望みますか?
この視点から考えてみると、お墓のあり方に対する見方も変わってくるかもしれません。
5.【次世代のための選択】子どもに負担をかけない供養とは

「お墓を継いでもらうこと」は、もしかすると、未来の世代に「お墓問題」を押し付けていることにもなりかねません。
日本では、今後も物価が上がり、収入がなかなか上がらない状況は続くでしょう。
格差が広がる中で、お墓の管理費用も、次世代にとってはさらに大きな負担になっていく可能性があります。
このままでは、お墓を管理し続けることが、物理的にも経済的にも難しくなるのは明らかです。
次世代に「お墓問題」を先送りするのではなく、私たち自身の代で、これからのお墓のあり方や供養の選択肢を真剣に検討する時期が来ているのではないでしょうか。
▲ 負担をゼロにする供養の形「海洋散骨」という選択
そんな中、お墓を持たない供養方法で、近年最も注目されているのが「海洋散骨」です。
散骨を選ぶ最大のメリットは、「承継者が不要」である点です。
管理費や維持費が一切かからず、まさに次世代に負担をゼロにする選択肢と言えます。
6.【まとめ】これからのお墓と供養の未来に出来ること

墓じまいの増加は、「管理の負担」「金銭的な負担」「承継者の不在」という、現代社会が抱える大きな課題を反映しています。
そして、その負担を未来の子孫に残さない選択は、決して間違ったことではありません。
もしあなたが今、お墓のことで少しでも負担や抵抗感を感じているのであれば、それはもう「負の遺産」と呼べるものになってしまっているのかもしれません。
高額な費用をかけてお墓を持たなければならない、そうしないと世間体が悪い――そんな古い風潮こそが、実は「負の遺産」なのかもしれません。
この現実に気づき、未来の子孫のために新しい供養のあり方を考える人こそが、本当に賢明な選択をしていると言えるのかもしれませんね。
東京や関東近県で海洋散骨をご検討でしたら、ぜひ海洋散骨オフィス一凛にご相談ください。
より多くのお客様の声はこちらからご覧いただけます! → 海洋散骨オフィス一凛のGoogle口コミはこちら
散骨でお困り、お悩みがありましたら、いますぐ下記までご相談くださいませ。
旦那のお墓は・・・女性のお墓に対する考え
今までの檀家制度は先祖のお墓に入る・・・これが当たり前でした。結婚した女性は、夫側のお墓に入る。 今まで当たり前だった、そんなお墓の習慣を疑問に思う女性が増えている事をご存知ですか?

公正証書遺言がオンライン対応になりました。
公証役場へ行かず自宅から作成できます。
条件と注意点を専門視点で解説します。

海洋散骨を選ぶ理由は一つではありません。
故人の願いを叶える供養としての選択。
そして遺骨の行方に向き合う現実的な選択。

同乗して海へ出る散骨には法律があります。
その船が本当に合法か確認できていますか。
後悔しない業者選びの基準を解説します。

100万円のお墓と30万円の樹木葬は何が違う?
なぜお寺は樹木葬を積極的に勧めるのか?
その裏側にある「儲かる仕組み」を解説します!

墓じまいは簡単だという空気があります。
でも現実は途中で立ち止まる人の方が多い。
それは覚悟不足ではなく仕組みの問題です。

お墓のある場所で管理者は違うってホント?
墓の購入者が全ての管理者ではないのです。
皆さんのお墓は誰に管理されていますか?

墓じまいで改葬許可証が出ないと言われた。
それは手続きミスではなく制度上の仕様。
知らないと止まる散骨の現場を解説。

終活の落とし穴、遺骨の行方に悩んでいませんか?
老人ホームへの入居で直面する供養の壁を解説します
後悔しない新しい選択肢をこの記事でご紹介します

墓じまい後の遺骨に迷っていませんか?
複数の骨壺や移動の負担は想像以上です。
後悔しない海洋散骨の進め方を解説します。

散骨は違法だと思っていませんか?
実は、正しい方法なら合法です。
不安を解消する法律とマナーを解説します。
散骨でお困り、お悩みがありましたら、いますぐ下記までご相談くださいませ。
散骨の一凛では遺骨の激安・格安の処分、他社よりも、どこよりも安い遺骨処分、海洋散骨をしております。