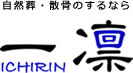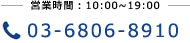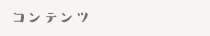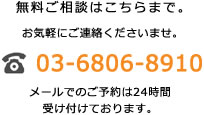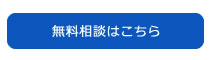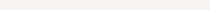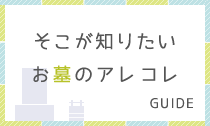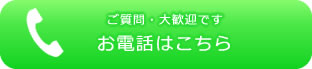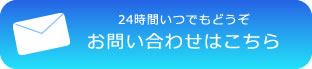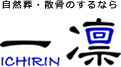「三途の川の渡し賃」は10円?日本全国お葬式の仰天ルール

あなたの葬送の常識は通用しないかも?
故人を見送る「葬儀」は、誰もが経験する儀式ですが、「決まった形式」で行われるものと思われがちです。
しかし、日本は地域ごとの歴史や信仰、地理的条件が色濃く残り、隣の県や市町村でさえ、葬送の常識がガラリと変わることがあります。
本記事では、故人への温かい想いが形になった、知られざる地域の風習を北から南までご紹介します。
ただし、これらの風習の中には現在では行われなくなっているものや、火葬場のルールで禁止されているものもあります。
地域の多様性を知る「読み物」としてお楽しみください。
1. 副葬品:棺に入れるものと託す想い

棺に入れる副葬品には、故人があの世へ旅立つ際、困らないようにという遺族の願いが込められています。
▲ 「三途の川の渡し賃」としての硬貨(北海道・東北など)
-
風習
: 棺の中に10円玉などの硬貨を入れる風習が、北海道や東北地方の一部に根強く残っています。これは、古くから伝わる「六文銭(冥銭)」の風習、つまり故人が三途の川を渡るための渡し賃の代わりとされています。また、火葬後に残った硬貨をお守りとして持つ地域もあります。
-
現代の事情(重要)
: 現在、硬貨(特に10円玉)は火葬の熱で溶けて火葬炉の台車にこびりつき、故障の原因となるほか、遺骨を変色させてしまうため、ほとんどの火葬場で副葬品として入れることは禁止されています。故人の旅立ちを願う場合は、紙に印刷された六文銭や手紙、写真などに替えるよう強く推奨されています。
▲ 故人が困らないための道具(福井・徳島など)
-
徳島県の裁縫道具
: 棺の中に針、糸、ハサミの裁縫道具一式を入れる風習があります。「故人があの世へ行っても裁縫に困らないように」という心遣いです。
-
福井県の異なる道具
: 福井県の一部では、男性の棺にカミソリ、女性の棺にハサミを入れる風習が見られます。
▲ 厄除けと身代わりの人形(近畿圏)
-
友人形(友引人形)
: 大阪や京都などの近畿圏を中心に見られる風習です。「友引(ともびき)」の日に葬儀を行うと故人が友を引いていくという迷信を避けるため、人形を身代わりとして棺に納めます。
2. 香典:お金のやり取りと地域ルール

弔意を表す金銭のやり取りにも、地域ごとの合理性や心遣いが色濃く反映されています。
▲ 香典に「領収書」が出る合理性(北海道)
-
風習
: 北海道では、葬儀の受付で香典の金額を確認し、その場で「香典代」の領収書を発行することがあります。 -
背景
: これは、会社関係者などが経費精算に使用できるように始まった、北海道ならではの合理的な風習と言われています。
▲ 「お見舞い」としての紅白香典(関東の一部)
-
風習
: 埼玉県秩父地方や新潟県など、関東の一部地域では、通夜の香典に、通常の不祝儀袋ではなく紅白の水引を使った袋を用いることがあります。 -
背景
: これは、香典袋の表書きを「お見舞い」とし、生前の入院中などにお見舞いに行けなかったお詫びを兼ねて弔意を表すという独特の心遣いによるものです。
▲ 故人ではなく「遺族」への見舞い(東海地方)
-
風習
: 愛知県や岐阜県、三重県では、通夜の際に香典とは別に、お菓子や果物といった食品を詰めた「お淋し見舞い」(または夜伽見舞い)を遺族に渡す習慣があります。 -
背景
: これは、夜通し故人に付き添う遺族の疲れを労い、寂しさを慰めるための見舞い品として贈られます。
3. 火葬のタイミング:前火葬と後火葬

葬儀の流れにおいて、最も大きな地域差の一つが、火葬のタイミングです。
▲ 遺骨が主役となる葬儀(東北・北海道など)
-
風習
: 関東以西の多くの地域が「お通夜→葬儀・告別式→火葬」の順で行う「後火葬」なのに対し、青森県、岩手県、北海道などの地域では、先に火葬を済ませ、遺骨を安置した状態で葬儀・告別式を行う「前火葬(骨葬)」が主流です。 -
背景
: 寒冷地で遺体の保存が難しかったこと、また、火葬場が遠方にあったため、先に火葬を済ませてから親戚が集まりやすいタイミングで儀式を行う方が合理的だった、などの説があります。
4. 儀式の違い:出棺と収骨の作法

葬儀の締めくくりにも、故人との別れを象徴する儀式が残っています。
▲ 故人との決別を宣言する儀式(西日本・埼玉の一部)
-
茶碗割り
: 西日本を中心に、埼玉県の一部などでも見られる風習です。出棺の際、故人が生前愛用していた茶碗を玄関先で割る儀式を行います。 -
意味
: これは、「もうこの世に戻ってくることはない」「この世での食事は終わった」という故人との永の決別と、魂を現世に留まらせないための意味が込められています。
▲ 拾う骨の量の違い(関東と関西)
-
風習
: 火葬後の収骨(お骨上げ)の際、東日本では基本的に全ての遺骨を拾い上げる「全収骨」ですが、西日本では喉仏や主要な一部の骨だけを拾う「部分収骨」が一般的です。 -
影響
: この習慣の違いから、関東と関西では使用される骨壺のサイズも異なります。
5. 現代の注意点:風習とルール

地域の風習は、故人を偲ぶ温かい気持ちから生まれていますが、現代では、安全面や法律的な理由から見直されているものが多くあります。
もし慣れない地域の葬儀に参列する場合や、ご自身の地域の風習に疑問を持った場合は、必ず事前に葬儀社の担当者に相談し、その地域の現在のルールと慣習を確認することが最も大切です。
火葬の際に故人を想う気持ちは、燃え残らない手紙や写真などに託しましょう。
東京や関東近県で海洋散骨をご検討でしたら、ぜひ海洋散骨オフィス一凛にご相談ください。
より多くのお客様の声はこちらからご覧いただけます! → 海洋散骨オフィス一凛のGoogle口コミはこちら
![]()
【人気記事一覧 01】
|
【人気記事一覧 02】
|
散骨でお困り、お悩みがありましたら、いますぐ下記までご相談くださいませ。
旦那のお墓は・・・女性のお墓に対する考え
今までの檀家制度は先祖のお墓に入る・・・これが当たり前でした。結婚した女性は、夫側のお墓に入る。 今まで当たり前だった、そんなお墓の習慣を疑問に思う女性が増えている事をご存知ですか?
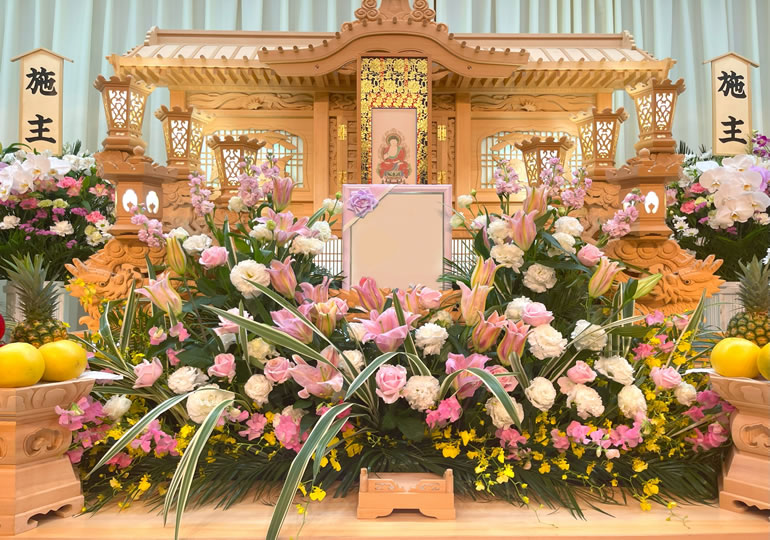
「そういえば、最近見かけないね」
街の葬儀屋さんが静かに消えていく。
その理由は、私たちの暮らしの中に。

「葬儀費用ってこんなに…」そんな不安を解消する「給付金制度」!
保険の種類によって、受け取れる金額や申請先は大きく変わります。
もらえるお金の種類と申請方法を詳しく解説します。

知られざる日本各地の葬送風習を紹介。
「三途の川の渡し賃」って本当なの?
あなたの常識、実は非常識かもしれません。

死んだら海に散骨してほしい——その想い、
実はご家族にとって大きな負担になることも。
この記事で、後悔しない準備を始めましょう。

樹木葬、海洋散骨に次ぐ空の選択肢。
バルーン葬の特徴と現実的な注意点。
他の自然葬との違いもあわせて解説。

いつか来る「その時」のこと考えてますか?
美しい手元供養も、終わり方で印象が変わる。
残された人が困らない出口の形を選びましょう。
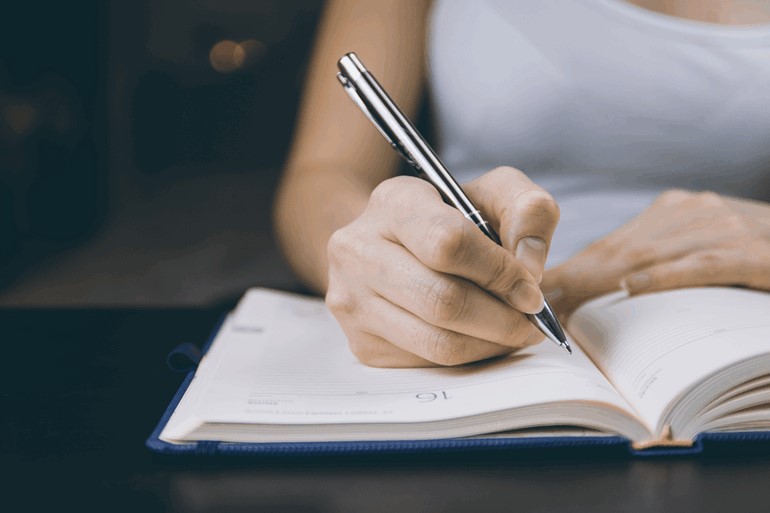
9割が途中で辞めるエンディングノート。
挫折の原因と続ける秘訣をわかりやすく紹介。
あなたの意思を家族にしっかり伝えよう。

ホームページの情報だけで決めていませんか?
実はトラブルの多い海洋散骨の現場。
後悔しない選び方を一緒に考えましょう。

「海に還りたい」その気持ち、伝えられる?
認知症になる前の備えが未来を変える。
大切な想いを形にする3つのポイント。

都心で増える「ビル型納骨堂」とは何か?
駅近で便利な自動搬送式が人気急上昇。
でも実は、見落としがちな落とし穴も…?
散骨でお困り、お悩みがありましたら、いますぐ下記までご相談くださいませ。
散骨の一凛では遺骨の激安・格安の処分、他社よりも、どこよりも安い遺骨処分、海洋散骨をしております。